うつは漢方で治るのか?(後編)
みなさんこんにちは(^^♪、前回からの続きになります。
前回のブログでは私が、うつに漢方治療を検討するのは以下のようなケースで、下記1~2についてお話しました。
1:うつ病自体が軽症であり、希死念慮(死んでしまいたい気持ち)がほとんど見られないケース。
2:季節変化や月経周期、更年期に伴いうつ気分が悪化するケース。
今回は3つ目の「既に十分な抗うつ薬が処方されているのに、なかなか良くならないケース」
に漢方治療が有効な理由についてです。
これまでは、抗うつ薬が薬効を発揮するメカニズムとして、脳内のセロトニンやノルアドレナリンといった脳内神経伝達物質の不足がうつ病を引き起こしているというモノアミン仮説が有力な時代がありました。
一時期は、「もはやうつ病は、怖い病気ではなくなった!」と、うつ病への勝利宣言がなされたような風潮もありましたが、現実はそう甘いものではありませんでした(;^_^A。
なぜなら抗うつ薬に反応を示さない患者さんが約3割ほどの割合で存在したからです。抗うつ薬はSSRI(選択的セロトニン再取り込み阻害剤)に代表されるように、脳内の神経細胞間におけるモノアミンを増加させることで薬効を発揮します。
しかし、モノアミンの上昇効果は、薬理学的にはすぐに表れるはずなのに、治療効果には数週間以上の期間を要するため、うつ病の原因が単なる脳内モノアミンの不足というものでは説明がつかなくなってきました。
その後、神経新生仮説(学習や記憶を司る、脳の海馬における、神経新生の低下がうつ病の発症に関係するという説)など、新しい学説も出てきましたが、いずれも決め手に欠けるところがありました。
しかし、ここ数年うつ病の原因として新しい仮説が注目されています。
それが「脳内神経炎症説」です。
この仮説では、「炎症」という生体反応について着目しています。
炎症というと歯肉炎とか、口内炎とか、患部が腫れたり赤くなって痛みを伴う状態を皆さんは連想されるでしょう。その通り、炎症とはウィルスや細菌が体に侵入してきたときに発動する「免疫反応」のことを指します。
免疫反応では、マクロファージやリンパ球といった免疫細胞が大暴れするわけですが、これらの細胞がお互いに連絡をとりあうための物質が、「炎症性サイトカイン」と呼ばれるタンパク質です。
ちなみに、免疫細胞から分泌されたサイトカインは、色々なルート(血流や副交感神経)を通じて、脳内のミクログリアと呼ばれる免疫細胞を刺激します。
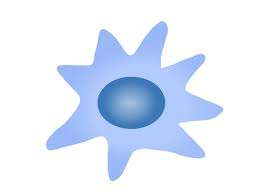
<ミクログリアのイラスト>
そして興奮したミクログリアが、炎症性サイトカイン以外にも活性酸素や一酸化窒素などの毒性物質を吐き出して、これらが脳の神経細胞にダメージを与えた結果、うつ病を発症するという説です。
この説は、脳内モノアミン仮説や神経新生仮説ともリンクします。例えば、炎症性サイトカインが上昇すると、IDO(indole amine 2,3- dioxygenase)という酵素が活性化し、セロトニンの合成が低下します。またこのIDOはセロトニンの分解を行う働きもあるので、炎症状態になればセロトニン不足の状態に陥りやすくなるのです。
また、ミクログリアが分泌したIL-1β(炎症性サイトカインの一種)が存在した状況下では、神経新生が損なわれる現象が観察されています。
つまり上流の神経炎症という現象により、下流のモノアミン不足、神経新生低下という2つの現象を説明することが可能となり、更には上流の神経炎症が続く限り、うつ病の治療効果は得られにくいという理由にもなります。
いつ、漢方の話が出てくるんだよ(# ゚Д゚)!!
と思われたそこの貴方、おまたせしましたm(__)m。
実は漢方薬の一群には、ミクログリアによる神経炎症を抑制することが分かっているものが幾つか存在します。代表選手としては、生薬、「柴胡」が含まれている、柴胡剤というグループです。
そして、私自身、柴胡剤により、抗うつ薬のみでは反応に乏しかったうつ病のケースを、大きく改善させたことが、臨床上、何度もありました。おそらくは柴胡剤に含まれる薬理成分が、脳内神経炎症の抑制につながったのではないかと、確信しています。
今回のブログは専門用語が多すぎて、少し難しかったかもしれません(;^_^A。
しかし、漢方薬は「古くて新しい治療薬」であることを、感じて頂ければ幸いです。


